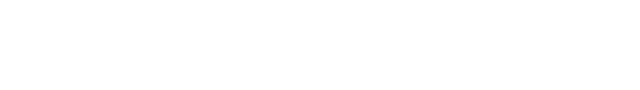五十肩は"治らない"?診断されたばかりで不安なあなたへ
「五十肩」と診断されたばかりで不安なあなたへ
「これって本当に治るの?」「ずっと肩が上がらなかったらどうしよう」── 病院で「五十肩ですね」と診断された瞬間、不安や疑問が一気に押し寄せてきたという方は多いのではないでしょうか。
五十肩(正式には「肩関節周囲炎/凍結肩」)は中高年を中心に多くの人が経験する疾患で、一時的に強い痛みや動かしづらさが生じることが特徴です。ただその一方で、「放っておいてもそのうち治る」「何年も痛みが続いたまま」という、まったく正反対の情報も飛び交っており、どう向き合えばいいのか迷ってしまう方も少なくありません。
特に、福岡のように医療機関の選択肢が多い都市では、「どこに通えばいいの?」「整形外科だけで大丈夫?」という戸惑いも出てきます。 そこで本記事では、診断を受けたばかりの方に向けて、「まず何をすればいいのか」「今後どうなっていくのか」といった不安を解消し、悪化させずにうまく向き合っていくための正しいステップをわかりやすく解説していきます。
「もう歳だから…」「しばらく我慢すればいいかも」──そんなふうに自分に言い聞かせる前に、一度立ち止まって読み進めてみてください。 これからの回復に向けた“最初の一歩”が、この記事の中にきっと見つかるはずです。
診断されたばかりの人が感じる不安とは?
「五十肩って結局、何をすればいいのか分からない」 「ちゃんと治るの?悪化したらどうしよう」 ──そう感じている方は、決してあなただけではありません。
五十肩と診断されたばかりの方が抱える不安には、ある共通点があります。それは、**「情報のあいまいさ」と「今後の見通しが立たないこと」**に対する不安です。ここでは、よくある疑問や不安に対して、できる限り具体的にお答えしていきます。
「本当に治るのか分からない」という不安
五十肩は一般的に自然回復が期待できると言われていますが、回復には半年〜1年以上かかることもあります。「治る」と分かっていても、痛みや動かしづらさが続く毎日に、先が見えず不安になるのは当然です。
ただ、近年では「放置すればよい」ではなく、「早い段階から正しい対応を取ることで回復期間が短縮される」という考えが主流になってきています。とくに福岡のように医療機関の選択肢が豊富なエリアでは、五十肩に特化した治療を行う整形外科やペインクリニック、リハビリ施設の利用で、改善のスピードが大きく変わることもあります。
「どこに行けばいいの?」という迷い
「整形外科に行けばいいの?でも、リハビリ施設とか鍼灸とかも聞くし…」 こうした戸惑いも、診断直後にはよくあるものです。答えとしては、「まずは整形外科で正確な診断を受けること」が基本。そのうえで、痛みの強さや進行段階に応じて、リハビリ・ペインクリニック・鍼灸などの併用を検討するのが、最近のスタンダードな流れです。
福岡には、肩の疾患に強い整形外科やリハビリ型のクリニックも多数あります。記事の後半では、治療施設の選び方や特徴についても詳しくご紹介していきます。
「このままずっと腕が上がらないのでは?」という恐怖
今は痛みや可動域の制限で思うように動かせないかもしれませんが、五十肩は正しいプロセスを踏めば、ほとんどの場合は回復が期待できます。
ただし、炎症が治まりきらないまま無理に動かすと、可動域が戻らないまま固まってしまうリスクもあるため、焦りは禁物です。今はまだ先が見えなくても、「段階的に良くなる」ということを頭に入れて、必要なときに医師のサポートを受けながら、適切なステップを踏むことが大切です。
こんなときは注意!自己流ケアが招く悪化のリスク
「病院に行くほどじゃないかも」「まずは自分で治せるか試したい」---そんな思いから、自己流で五十肩をケアしようとする方は少なくありません。インターネット上には五十肩に効くとされるストレッチやマッサージの動画、記事があふれており、「これなら簡単そう」と気軽に実践する人も多いでしょう。
しかし、自己流のケアには思わぬ落とし穴があります。
タイミングを間違えると“逆効果”に
五十肩は「炎症期」「拘縮期」「回復期」という3つのステージに分かれており、それぞれで必要な対応が異なります。
炎症期(急性期)
突然強い痛みが出る。夜間痛がひどく、肩がじっとしていてもズキズキする。→ この時期は基本的に“動かさない”ことが大切。無理にストレッチをすると、炎症が悪化してしまいます。
拘縮期(慢性期)
痛みが落ち着き始めるが、肩の可動域が著しく制限される。→ この時期は少しずつ“動かす”ことが必要ですが、やみくもに動かしても改善しません。専門家の指導のもとで、正しい運動療法を行うことが重要です。
回復期
肩の動きが戻ってくる時期。→ ストレッチや筋トレが効果を発揮するタイミング。ただし「痛気持ちいい」を超える刺激はNG。焦りは禁物です。
自己流ケアの最大のリスクは、自分が今どの段階にいるのかを判断できないこと。 痛みがあるからと冷やしすぎたり、逆に温めて悪化させたり、炎症期にストレッチをして症状を長引かせてしまったりする例は後を絶ちません。
よくある「自己流で悪化」したケース
実際に福岡市内のクリニックで聞かれる例としては、次のようなものがあります。
- YouTube動画を見て毎日肩回しをしていたが、痛みが悪化して夜も眠れなくなった
- 「血行が悪いから温めよう」とサウナに通っていたら腫れと痛みがひどくなった
- 「動かしたほうが治りが早い」と言われ、スポーツジムで無理にトレーニングをして症状がぶり返した
- ストレッチ中に「ズキッ」と痛みが走ったが我慢して続けた結果、腕がさらに上がらなくなった
こうしたケースは、決して特殊なものではありません。**「良かれと思ってやったことが、結果的に状態を悪化させる」**ということが、五十肩では実際によく起こるのです。
医療機関とセルフケアは“補完関係”
もちろん、すべてのセルフケアが悪いというわけではありません。五十肩の回復には、適度な運動や温熱・冷却ケア、姿勢の見直し、生活習慣の改善などが欠かせません。しかし、それらはあくまで「医師や理学療法士の指導を受けたうえで、段階に合わせて行う」ことが前提です。
福岡には、整形外科やペインクリニック、リハビリ特化型の医療施設、鍼灸院など、五十肩に対する多様な専門機関が存在するため、専門家の判断を仰ぎながら、効果的なセルフケアを継続することで、回復を加速させることができるのです。
セルフケアに取り組む前にチェックしたい3つのこと
- 今の自分の五十肩はどの段階か? → 痛みの強さ、動きの制限度、夜間の痛みなどを医師に相談し、段階を把握しましょう。
- ストレッチや運動は「痛くない範囲」でやっているか? →「痛いけど動かしたほうがいい」は間違い。強い痛みを我慢する運動は逆効果です。
- 本当に“自分で治す”べき段階か? → 治療が必要な時期を自己判断で逃すと、回復までの時間が長くなります。
自己流ケアの選択は、時に「治るはずの肩を悪化させる」リスクにもつながります。迷ったときは我慢せず、専門機関で一度相談することが、回復への確実な第一歩です。
五十肩と間違えやすい他の疾患とは?
「何ヶ月も通院しているのに、肩の痛みが全然よくならない」 「医師から五十肩と言われたけれど、リハビリしても変化がない」
そんな方は、一度“診断そのもの”を見直してみる必要があるかもしれません。実は、五十肩に似た症状を持つ疾患は複数存在します。ここでは、五十肩とよく間違えられる3つの代表的な疾患について紹介し、それぞれの特徴や見分け方を解説します。
有痛性腱板断裂(ゆうつうせいけんばんだんれつ)
五十肩と最も間違われやすい疾患のひとつが、腱板断裂です。
腱板とは、肩関節を覆う筋肉や腱の集合体のこと。これが加齢や外傷、使いすぎにより断裂すると、肩を動かす際の痛みや筋力低下が起こります。五十肩と違って、「ある特定の動きだけが極端にできない」「腕に力が入らない」などの症状が目立つのが特徴です。
主な見分けポイント
- 痛みとともに「腕に力が入らない」感覚がある
- 夜間痛が強く、寝返りで目が覚める
- リハビリを続けても改善が見られない
- 肩の筋肉(特に三角筋の下)が痩せてくる場合も
画像診断(MRIや超音波)によって明確に診断が可能なので、「五十肩と言われたけど動かすと違和感が強い」という方は、再度検査を受けることをおすすめします。
ただし、腱板が(部分)断裂してしていても痛みがない方も多くいらっしゃいます。違いとしては、炎症が起きているかと腱板周囲の筋肉等でサポートできているかです。炎症を減らし、リハビリを進めていくことが重要です。
石灰沈着性腱板炎(せっかいちんちゃくせいけんばんえん)
突然の激痛と発熱を伴うことがあるこの疾患も、五十肩と混同されやすいもののひとつです。
肩の腱に石灰(カルシウムの結晶)が沈着し、それが炎症を引き起こします。ある日突然、肩に刺すような激痛が走り、腕をまったく動かせなくなることもあります。特徴的なのは「急な痛みの発症」と「石灰がレントゲンやエコーで写る」という点です。
主な見分けポイント
- 朝起きたときに急に肩が動かなくなった
- 腫れや熱感がある
- レントゲンやエコー検査で白く石灰沈着が確認できる
- 発症年齢は比較的若め(40〜50代女性に多い)
急性期には消炎鎮痛剤や注射での対応が有効ですが、石灰が大きい場合は吸引除去が必要になることもあります。
頚椎症(けいついしょう)による神経障害
肩の痛みが“神経由来”である場合も少なくありません。
五十肩と誤解されがちなのが、頚椎症など首のトラブルからくる神経障害です。首の椎間板が加齢などで変形し、神経を圧迫することで、肩や腕にしびれや痛みが広がるケースです。
主な見分けポイント
- 肩の痛みだけでなく、腕〜指先にしびれがある
- 肩を動かさなくても神経痛のような不快感がある
- 首の動きで痛みが変化する(上を向くと悪化など)
- 筋力の低下や感覚の鈍さを伴うことがある
整形外科での診察や頚椎MRI検査によって診断されます。肩の動きよりも“神経的な症状”が強いと感じたら、五十肩ではない可能性を疑いましょう。
「本当に五十肩?」と迷ったら…
五十肩は、「除外診断」と呼ばれる方法で診断されることが多いです。つまり、他の病気の可能性を一つずつ消去していった先に、「五十肩(肩関節周囲炎)」という診断がつくという流れです。
しかし、最初の段階で誤診があると、いくら治療を頑張っても効果が出ない…ということになってしまいます。
だからこそ、以下のような場合は一度別の病院の受診を検討してみましょう。
- 数か月以上治療を続けてもまったく改善が見られない
- 痛みが左右差なく拡がっている(両肩に同じ症状がある)
- リハビリをしてもむしろ悪化していると感じる
- 神経症状やしびれがある
病院を変えるべきタイミングのすすめ
「この治療で合っているのだろうか?」 「ずっと通っているのに全然良くならない」 そんな不安を抱えながらも、なんとなく通院を続けてしまっている方は少なくありません。
ですが、五十肩のように長期化しやすい疾患にこそ、“今の医療方針は本当に正しいのか”という視点が欠かせません。改善が見られないときこそ、「病院を変える勇気」が、次の一歩を切り開いてくれるのです。
通院を見直すべき3つのサイン
3ヶ月以上の通院でも改善が見られない
リハビリや薬を続けても、痛みの強さや可動域の制限に変化がない場合、治療方針がそもそも合っていない可能性があります。特に、初期の炎症期が終わっても動きがまったく戻らない、痛みが増しているといった場合は、別の視点からの評価が必要です。
毎回同じ対応だけで治療に変化がない
ただ湿布や痛み止めを出されるだけ、通るだけのリハビリだけ――。このような“ルーティン化した治療”が続くなら、そのまま通い続けるメリットは薄いかもしれません。医師があなたの状態を定期的に再評価してくれているかどうかが大切です。
他の疾患の可能性が除外されていない
前章でも紹介したように、腱板断裂や神経由来の痛みが見逃されているケースもあります。きちんとMRIやエコーなどの画像診断が行われているか、他の疾患との違いを説明してもらえたかを思い出してみましょう。
セカンドオピニオンは“治療に対する責任”を持つ行動
セカンドオピニオンは、「今の病院を否定するためのもの」ではありません。あくまでも、患者が納得できる治療を選ぶための前向きなステップです。
他の医師から別の視点の意見を聞くことで、「やっぱり今の治療で合っているんだ」と再確認できる場合もありますし、逆に「こんなアプローチもあるのか」と視野が広がることもあります。
特に五十肩のように診断が曖昧になりやすく、治療が長期化しがちな症状には、この“確認プロセス”が非常に有効です。
福岡でセカンドオピニオンを受けられる医療機関の選び方
福岡市内には、セカンドオピニオンを積極的に受け入れている整形外科やペインクリニック、また肩専門外来を掲げる施設も増えています。
選ぶ際のポイントは以下の通りです:
- 肩関節の診療実績が豊富な医師が在籍している
- MRIや超音波などの検査体制が整っている
- リハビリスタッフとの連携がスムーズ
- カウンセリングをしっかり行ってくれる雰囲気がある
- 炎症と拘縮に対してアプローチしている
また、「五十肩」と診断されたあとに、別の医療機関で「実は腱板断裂だった」と言われた事例もあるため、症状が重い方ほど、より専門性の高い医師に相談することが大切です。
「変えること=悪いこと」ではない
日本では、医療機関を変えることに罪悪感を持ってしまう方が多い傾向にあります。しかし、あなたの身体に責任を持てるのは、あなた自身だけです。
「このまま通っていて本当に良くなるのか?」 「他の選択肢があるなら知っておきたい」
そう思った時が、“行動するタイミング”です。
五十肩は放置すればするほど、肩関節が硬くなり、回復にかかる時間も長くなってしまいます。後悔する前に、もう一度治療のスタート地点に立ってみることを、ぜひ検討してみてください。
まとめ|「診断されたあと」が、正しい選択の始まり
「五十肩と診断されたけど、このまま痛みが続くのでは?」「治療って本当に効くの?」と不安になる気持ちは、誰にでもあるものです。特に福岡のように医療機関の選択肢が多い地域では、「どこに行けばいいの?」「何が正解なの?」と悩んでしまう方も少なくありません。
しかし大切なのは、焦らずに“今の自分の症状と段階”を理解し、信頼できる医師や治療者と一緒に最適なプランを立てていくことです。痛みが強い時期には無理をせず、回復期には少しずつ動かす。段階に応じたケアをすることで、五十肩は改善の道をたどることができます。
また、整形外科だけでなく、痛み専門のペインクリニックや鍼灸など、選択肢を広げてみることも大切です。「この治療法で合ってるのかな?」と不安を感じたら、迷わずセカンドオピニオンを。あなたの体に合ったアプローチは、必ず見つかります。
診断は、ゴールではなく“スタート”です。怖がる必要はありません。今後の治療選びに前向きな視点を持つことで、きっと不安は「安心」に変わっていくはずです。
ぜひ一度福岡ペインケアクリニックでご相談ください。